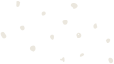がんは人においても死因の第1位を占めています。その早期発見を目的として、市区町村は国の補助を受け、安価な自己負担でがん検診が受診できるようになっています。行政からのお手紙をご覧になったこともあるでしょう。
犬も猫も、腫瘍は死因の第1位となっていますが、人医療のようながん検診を定期的に行う習慣が未だないのが現状です。人医療では、科学的根拠に基づく検査法が確立されていますが、獣医療においてはまだ確立された検査法がないのが実情です。
また、獣医療の世界では「がん検診」というワードもまだまだ一般化されていません。なぜ、一般化されていないかというと、①客観的数値による診断方法が少ない、②獣医師の力量に大きく左右される、という2点が要因であると考えます。
獣医療におけるがん検診は、レントゲン検査やエコー検査などの画像診断が軸となります。血液検査などの客観的数値で診断を行うのではなく、獣医師が目で見て診断をおこなうため、獣医師の力量によって左右されることになってしまうのです。
腫瘍が疑われる状態であれば、症状や血液検査の数値などから、ある程度発生部位に目途をつけて検査を行うこともできます。一方で、
まだ症状の出ていない状況下での健康診断では、全身をくまなく診て腫瘍の疑わしい部位を探る必要があります。
当然、見落としがあってはなりませんので、多くの動物病院ではリスクを避けるため、がん検診という言葉を使用することを避ける傾向にあると言えます。
当院は院長が全国で49名強しかいない獣医腫瘍科におけるプロフェッショナルの証である獣医腫瘍科認定医Ⅰ種を取得しています。これまでに数多くの腫瘍症例の早期発見・早期治療に携わってきました。
がんは早期に発見できれば、平均寿命(余命)を延ばすこともできますし、生涯医療費を抑えることも可能となります。早く見つけることにはメリットしかないのです。
1頭でも多くのワンちゃん・猫ちゃんをがんから救いたい。その想いで腫瘍の知識と経験を積み重ねてきました。その経験と実績を活かして、がんの早期発見のためのがん検診をご提案してまいりたいと考えております。
犬で多い腫瘍のTOP10
乳腺腫瘍(乳がんを含む)
雌犬で最も発生が多い腫瘍で、雌の全腫瘍の約50%を占めます。避妊していない高齢雌に多く、良性と悪性の割合は概ね半々です。悪性の場合は肺や肝臓へ転移しやすく(肺転移は呼吸困難の原因に、肝転移は食欲不振など全身衰弱の原因になります)、直接の死因になることもあります。腹部の乳腺にできるしこりとして飼い主が発見しやすく、早期の避妊手術で発生率を大幅低減できます。なお犬の乳腺腫瘍は約半数が良性ですが、残り半数は悪性で進行が速いため注意が必要です。
肥満細胞腫
免疫に関与するマスト細胞由来の皮膚の悪性腫瘍です。犬の皮膚腫瘍で最も多く、全皮膚腫瘍の15~20%以上を占めます。中高齢犬(平均8歳前後)に好発し、日本犬種(柴犬など)で多くみられる傾向があります。皮膚や皮下のしこりとして発見され、見た目では良悪の判断が難しいため細胞診や生検で確定診断します。局所再発やリンパ節・脾臓・肝臓・骨髄など全身への転移が起こりやすい腫瘍で、グレードによっては非常に悪性度が高く迅速な対応が必要です。
リンパ腫
リンパ節など免疫細胞の組織が腫瘍化する癌で、犬では非常によく見られる悪性腫瘍の一つです。悪性リンパ腫は犬の悪性腫瘍の中で発生数上位(約15%)を占め、全身のリンパ節の腫れ、食欲元気消失などで気づかれます。多中心型(全身型)が犬では半数以上と最多で、次いで消化管型(腸や胃)などがみられます。ゴールデン・レトリーバー、コリー、アメリカン・コッカー・スパニエルなど特定犬種で比較的発生が多いとの報告があります。
悪性黒色腫
メラニン産生細胞由来の悪性腫瘍(メラノーマ)で、口腔内に最も多発する腫瘍です。口の中や指趾部、眼周囲などに発生しやすく、黒色ないし不規則色素のしこりや潰瘍として見つかります。極めて悪性度が高く転移しやすいのが特徴で、局所切除や抗がん剤治療を行っても遠隔転移によって死亡するケースが多い難治性の癌です。高齢の小型~中型犬に多く、口臭・よだれ・口内出血などで気づくことがあります。
骨肉腫
骨の悪性腫瘍で、犬の骨腫瘍では最も一般的です。発生部位の典型は四肢の長骨(肩や膝の周辺など)で、主に大型犬・超大型犬の中高齢で発症リスクが高いとされます。病変部の骨破壊によるびっこ(跛行)や腫れが初発症状です。進行が速く肺などへの転移率も高いため攻めた治療が必要で、四肢の場合は断脚手術と抗がん剤による治療が一般的です。発生はゴールデン・レトリーバー、ラブラドール、ロットワイラーなどに多い傾向が報告されています。また顎骨の骨肉腫は中小型犬にもみられ、局所再発しやすいものの遠隔転移は四肢より少ないとされています。
血管肉腫
血管の内皮細胞由来の悪性腫瘍で、特に脾臓に発生する例が多い癌です。ゴールデン・レトリーバーやジャーマン・シェパードなど大型犬の8歳以上で発症が多いと言われますが、小型犬でも発生し得ます。脾臓の悪性腫瘍の約45–50%を血管肉腫が占めるとの報告があり、他に心臓(右心房)・肝臓・皮膚・皮下組織など様々な部位に発生します。脾臓血管肉腫は破裂による腹腔内出血を起こしやすく、突然の虚脱や貧血症状で気づかれることが多いです。非常に悪性度が高く転移もしやすいため、早期発見が困難ながらも日頃から超音波検査等でチェックし、疑わしい場合は脾臓摘出を含む迅速な対応が推奨されます。
脂肪腫
脂肪細胞由来の良性腫瘍で、中高齢犬にしばしば認められる皮下のやわらかい腫瘤です。犬の良性腫瘍の中で発生率が高く(良性腫瘍症例の約15%)、特に肥満傾向の中年齢以上の犬で体幹部(胸部や腹部、腿の内側など)にできることが多いです。触ると軟らかく可動性のある塊で、痛みは通常ありません。基本的に悪性化(脂肪肉腫への移行)はまれですが、大きくなりすぎると運動障害や生活の質低下を招くため、場所によっては外科的切除が選択されます。
肛門周囲腺腫
肛門の周囲にある脂腺由来の良性腫瘍です。男性ホルモンの影響で未去勢雄犬の高齢犬に非常によく発生し、小豆大からクルミ大のコブが肛門周囲や尾の下面に複数できることがあります。良性で遠隔転移はしませんが、大きくなると潰瘍化して出血したり排便障害を起こすことがあります。根治には外科切除と去勢手術(再発予防のため)を併施するのが一般的です。一方、雌犬や去勢雄で似た部位にできる腫瘤は肛門嚢アポクリン腺癌といった別の腫瘍の可能性があるため注意が必要です。
扁平上皮癌
表皮や粘膜上皮に生じる悪性腫瘍です。犬では口腔内の扁平上皮癌と指趾(爪床)の扁平上皮癌が代表的で、悪性度は中等度ながら局所浸潤性が強い傾向があります。口腔内では歯肉や舌に発生しやすく、悪臭やよだれ、出血などで気づきます。指趾のものは爪が変形・脱落したり指が腫れて痛むため跛行を呈します。発生頻度は犬の悪性腫瘍中数%程度ですが、大型犬の指趾腫瘍や短頭種の口腔腫瘍として時にみられ、外科切除が第一選択です(指趾の場合は断指術)。転移は稀ですが、再発しやすいので追加の放射線治療や抗がん剤を検討することもあります。
皮膚組織球腫
若い犬(平均年齢3歳未満)に好発する良性腫瘍です。免疫細胞由来の腫瘤で、頭部や四肢に単発し、小さく丸い赤色~肌色のドーム状に盛り上がるしこりとして現れます。子犬・若齢犬の皮膚腫瘍で最も頻繁にみられるタイプで、自然に消退することも多い良性の腫瘍です。見た目が他の悪性腫瘍と区別しにくいため、細胞診で組織球腫と確認できれば経過観察しますが、急速に大きくなったり感染を起こす場合は外科的に切除します。
猫で多い腫瘍のTOP10
リンパ腫
猫で最も一般的な腫瘍で、全悪性腫瘍の約45%を占めます。主な発生形式は消化器型リンパ腫(胃腸に発生)が最多で猫リンパ腫の約45.5%を占め、次いで鼻腔内リンパ腫(約13.6%)、胸腺型(縦隔型)リンパ腫(11.4%)などが報告されています。消化器型は嘔吐や下痢・体重減少など慢性的な消化器症状で気づかれ、鼻腔内リンパ腫では鼻づまり・鼻血など鼻炎状の症状がみられます。猫白血病ウイルス(FeLV)感染と関連するリンパ腫もあり、若年で発症する縦隔型リンパ腫はFeLV陽性であることが多いです。
乳腺腫瘍
未避妊の雌猫で発生する頻度が高い腫瘍で、雌猫の腫瘍の約17%を占めます。非常に悪性度が高く約80~90%が癌(悪性腫瘍)であることが猫の乳腺腫瘍の大きな特徴です。発生年齢は10~12歳の高齢雌に多く、避妊手術の実施時期が早いほど発生率が低下します(生後6ヶ月未満で91%リスク減)。腹部の乳腺に沿ったしこりとして触知され、進行すると潰瘍化や出血を伴います。肺への転移が約半数の症例で生じ、咳・呼吸困難などを引き起こすため予後不良です。治療は外科的に乳腺を広範囲に切除するのが基本で、再発転移を防ぐため片側~両側の全乳腺切除が推奨されます。早期発見・治療でも再発が多い難治性腫瘍であり、定期的にお腹を触診して小さなしこりの段階で発見することが重要です。
扁平上皮癌
表皮や粘膜の扁平上皮細胞由来の悪性腫瘍です。猫では口腔内に発生する癌として最も多く、高齢猫の舌下や歯肉に生じることが多いです。また白毛の多い猫では日光曝露の多い耳介先端や鼻梁に皮膚型扁平上皮癌が発生しやすいことも知られます。口腔内のものは局所で非常に浸潤的に増大し、顎骨を破壊したり大きな腫瘤となるため外科切除が困難です。転移はまれですが増殖速度が速く、十分な栄養摂取や口腔ケアが困難になることで衰弱します。皮膚型の場合は耳先や鼻に潰瘍化病変を作り、外科切除または凍結療法などで病変部位を除去します(耳先なら耳介切除術)。猫の扁平上皮癌は全悪性腫瘍の約9%と報告されています。
肥満細胞腫
マスト細胞が腫瘍化した疾患です。犬では悪性が多いのに対し、猫の肥満細胞腫は良性の場合が多い点が特徴です。皮膚に生じる皮膚型肥満細胞腫が大半(猫の肥満細胞腫症例の約95%)で、これは良性腫瘍群に分類されます。耳介や頭頸部・四肢の皮膚下に小さなしこりとして現れ、比較的ゆっくりと成長します。外科的切除で完治することが多く、転移はまれです。一方、脾臓や消化管に発生する内臓型肥満細胞腫は頻度が低いものの非常に悪性度が高く、脾臓型では脾腫により食欲不振や体重減少、貧血などを呈し、早期の脾臓摘出が推奨されます。
繊維肉腫(注射部位肉腫を含む)
線維芽細胞由来の悪性腫瘍で、皮下組織から発生する硬いしこりとして気づかれます。中高齢猫に多く、自発的に発生するもののほかワクチンや注射部位で発生することがある特殊な肉腫として知られます(ワクチン関連肉腫)。侵襲的に周囲組織へ浸潤しやすく、外科切除しても再発しやすい厄介な腫瘍です。転移率は20%前後とされていますが、局所制御が難しいため予後はあまり良好ではありません。発生は肩胛骨周囲や脊背部、大腿部など皮下のどこにでも起こりえます。ワクチン接種部位にしこりが残る場合は早めに細胞診などで確認し、急激に増大する場合は広範囲切除術を検討します。
鼻腔内腫瘍
鼻腔内に発生する腫瘍の総称で、猫ではリンパ腫に次いで鼻腔の癌が多いとされます。代表的なのは鼻腔内の腺癌(鼻腔内癌)で、中高齢の短頭種以外の猫(長頭種)に発生しやすい傾向があります。くしゃみや鼻汁(鼻水)、鼻出血、呼吸時のいびき音など慢性鼻炎と似た症状が続き、抗生剤を使っても改善しない場合に疑われます。診断には全身麻酔下での鼻鏡検査や組織生検が必要です。鼻腔内腫瘍は局所浸潤が強く脳や眼窩に及ぶこともありますが、転移は比較的少ないため、放射線治療や外科的切除で延命が図られます。
甲状腺腫(甲状腺機能亢進症)
甲状腺の良性腫瘍(腺腫)または過形成によって甲状腺ホルモンが過剰分泌される病態です。高齢猫の約10%前後が罹患する非常にありふれた内分泌腫瘍で、発症年齢のピークは13歳前後です。多飲多尿・多食なのに体重減少・筋肉萎縮する、といった特徴的な症状で気づかれます。喉にある甲状腺が腫れて触知できる場合もあります。良性腫瘍(腺腫)のことが大半ですが、まれに甲状腺癌(悪性)も報告されています(甲状腺腫瘍全体の5%未満)。治療は内科管理(抗甲状腺薬の投与)や外科的甲状腺摘出、アイソトープ療法(放射性ヨウ素)などで、適切に管理すれば予後良好です。
骨肉腫
犬ほど多くありませんが、猫にも骨の悪性腫瘍である骨肉腫が発生することがあります。頻度は猫の悪性腫瘍全体の約6%と報告され、犬に比べ転移率が低い傾向があります。好発部位は四肢の長骨や顎骨で、高齢猫に発症がみられます。症状は患肢の跛行や腫脹、疼痛で、X線検査で骨の溶解像が確認されます。治療は患肢の断脚術が選択されることが多く、断脚のみでそのまま長期生存する例も犬より多いです。ただし顎骨の骨肉腫は局所再発しやすく、切除範囲を確保できない場合は再発と付き合いながらの対症療法となります。
胸腺腫
胸腔内の胸腺上皮由来の良性腫瘍で、中高齢の猫に発生します。縦隔(胸腺のある部位)に腫瘤ができる縦隔型リンパ腫との鑑別が必要な疾患です。胸腺腫は良性で転移しませんが、腫瘤が大きくなると肺を圧迫して呼吸困難や胸水貯留を引き起こします。前肢に力が入らなくなるホルネル症候群や筋無力症(重症筋無力症)を副症状として呈することもあります。確定診断には胸部画像検査や細胞診・生検が必要です。治療は外科的摘出が可能なら予後は比較的良好です(術後に症状が治ることもあります)。一方、手術不能な場合は胸水除去やステロイド投与などの対症療法となります。
多発性骨髄腫
免疫グロブリン産生型の形質細胞が腫瘍化する血液の癌です。猫では犬ほど頻繁ではないものの、高カルシウム血症や貧血、免疫不全(易感染)など多彩な症状を呈する難治疾患です。7~10歳以上の高齢猫に発生し、元気消失、食欲不振、体重減少、出血傾向(鼻血や歯肉出血)などで気づかれます。確定診断には骨髄検査を行い、異常形質細胞が増殖していることを確認します。治療はメルファランやプレドニゾロンなどの抗がん剤治療で寛解を目指しますが、完治は難しく平均生存期間は1年未満とされています。症状を緩和しながら生活の質を維持する緩和ケアも重要になります。
早期発見で得られるメリット
1.費用面のメリット
早期発見により、生涯医療費が低く抑えられる可能性が高まります
がんなどの腫瘍疾患では、進行すればするほど手術・抗がん剤・放射線治療などの費用が加算され、総額が数十万〜数百万円に達することもあります。例えば、犬の乳腺腫瘍の手術に通常10〜20万円、抗がん剤治療に毎月5〜10万円、放射線治療では合計50〜100万円という高額になるケースも報告されています。
健康診断や定期検診での早期発見であれば、少ない負担で済む可能性が高まります。健康診断の料金相場は比較的リーズナブル(血液検査・エコー・レントゲンなどで数千〜数万円)で、重症化した後の治療費と比べて、早期診断の医療費は相対的に安くなる傾向があります。
また、「腫瘍科」情報では、高齢犬の45%が腫瘍関連で亡くなるという報告もあり(犬全体では約23%)、腫瘍疾患の頻度の高さを考えると、早期介入による医療費削減の意義は非常に大きいです。
2.平均寿命の延長
早期発見により、平均寿命や余命を延ばすことができます
犬の乳腺腫瘍では、早期(3cm未満かつ転移なし)の段階で手術をすれば、術後1年以上、場合によっては3年以上生きられるケースもあります。一方、進行期や転移ありの場合、余命は6ヶ月〜1年、末期では数週間〜1ヶ月以内という例もあります。
犬のリンパ腫(特に多中心型の高悪性度)を治療せず放置した場合、平均余命はわずか90日程度にとどまります。早期治療開始が余命延長の鍵となることが示唆されています。
猫のがんは悪性腫瘍の比率が高く(87.7%)、進行すると生命を脅かしやすいことが知られています。たとえば、口腔内の扁平上皮がんはほとんど悪性(約80%)で、進行するほど手術による完治が困難になるため、早期発見・外科切除が重要です。
また、猫の平均寿命は年々延びており、15歳以上の長寿猫も増えている一方で、高齢になるほどがんリスクも上昇します。早期発見はこの長寿化時代において、愛猫の寿命をさらに延ばすためにも極めて重要です。
3.早期発見のメリット
費用面
進行したがん治療は高額(数十万〜数百万円)。
早期発見なら治療の負担が軽減されやすい。
平均寿命・余命の延長
早期治療では寿命が大幅に延びることが多く、進行すればその分短命に。
特に乳腺腫瘍・リンパ腫などで顕著。